
注目の成分
βカロテン、カリウム、モノテルペン酸、セスキテルペン酸
三つ葉に含まれる成分に期待される効能
動脈硬化予防、ストレス解消、精神安定、胃もたれ解消、食欲増進、肌荒れ解消
三つ葉の抗酸化作用
三つ葉にはカリウムなどのミネラル類や、βカロテン、ビタミンB群などのビタミン類が含まれ、特に糸三つ葉にはβカロテンが豊富に含まれています。
βカロテンは抗酸化作用が非常に強く、活性酸素を無毒化してガン予防に働く他に、体内で必要なだけビタミンAに変わります。
ビタミンAは皮膚や粘膜を強くして、体外からの異物の侵入を抑えて免疫力を高めたり、腸管の消化吸収能力を高めてくれます。
食欲を高めて胃もたれを防ぎ血の巡りを改善に期待

特有のさわやかな香りはクリプトテーネンとミツバエンという成分で、食欲を高め胃もたれを防ぐ作用や、神経の興奮を鎮めストレスによるイライラやのどの詰まり感、肩こり、肌荒れなどを緩和して精神を安定させる効果に期待できます。
イライラを鎮め精神をリラックスさせる効果があるので、精神の起状によりかんの虫が起きやすくなっている子供や、精神的に不安定な状態の時に発生する夜泣きや不眠症の改善に期待できます。
血液の滞りをなくして血液循環をよくする働きがあるので、高血圧や動脈硬化の予防など病気の誘因の軽減に効果があります。
炎症を鎮める作用や解毒作用、鎮静作用、痰を取り除く作用があるので、歯痛、歯茎の腫れ打撲、捻挫による腫れ、頭痛、生理痛などの軽減に効果が期待されます。
豊富に含まれているビタミンKは、じょうぶな骨づくりに欠かせない栄養素で、カルシウムの骨への沈着を助ける働きや、止血作用に期待できます。
セリ科ミツバ属 三つ葉の栄養成分

可食部100gあたり 日本食品標準成分表2015年版(七訂)参照
| 根三つ葉 生 | 根三つ葉 ゆで | 糸三つ葉 生 | 糸三つ葉 ゆで | |
| 食物繊維 | 2.9g | 3.3g | 2.3g | 3.0g |
| カリウム | 500mg | 270mg | 500mg | 360mg |
| カルシウム | 52mg | 64mg | 47mg | 56mg |
| βカロテン | 1700μg | 2100μg | 3200μg | 4100μg |
| ビタミンE | 1.1mg | 1.4mg | 0.9mg | 1.3mg |
| ビタミンK | 120μg | 150μg | 220μg | 250μg |
| ビタミンB2 | 0.13mg | 0.05mg | 0.14mg | 0.08mg |
| ビタミンC | 22mg | 12mg | 13mg | 4mg |
単位:μg(マイクログラム)とは、
1g=1000mg=1000000μg
1μg=0.001mgになります。
根三つ葉
おいしい時期は3月~4月
土寄せし軟白しており、根がついたまま出荷されるもので、茎の下部は白く茎は太くなっています。糸三つ葉に比べ風味が強く、根も食用になります。
糸三つ葉
おいしい時期は周年
軟白せず根元まで日光にあてて栽培する為、茎まで緑色で、三つ葉の中でもっとも栄養価が高くなっています。関西から広まり、青三つ葉とも呼ばれます。
日本人の1日に必要な食事での摂取基準量(2015年版)
| 30歳~49歳 男性 | 30歳~49歳 女性 | |||
| 推奨量 | 耐用上限量 | 推奨量 | 耐用上限量 | |
| 食物繊維 | 20g以上 | – | 18g以上 | – |
| カリウム | 3000以上 | – | 2600以上 | – |
| カルシウム | 650mg | 2500mg | 650mg | 2500mg |
| ビタミンA | 900μg | 2700μg | 700μg | 2700μg |
| ビタミンE | 6.5mg | 900mg | 6.0mg | 900mg |
| ビタミンK | 150μg | – | 150μg | – |
| ビタミンB2 | 1.6mg | – | 1.2mg | – |
| ビタミンC | 100mg | – | 100mg | – |

おいしい三つ葉の選び方
葉は緑色が鮮やかでみずみずしく、茎は白く軸に張りがあり、香りが強いものをえらびましょう。
保存方法
乾燥すると香りがなくなるので、キッチンペーパーで包みビニール袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存します。
食べ合わせによる相乗効果

三つ葉+さやいんげん:食欲増進
三つ葉+ゆず:イライラ解消、のどの詰まり感改善
三つ葉+コンニャク:肌荒れ解消
三つ葉+ごま油:美肌づくり
三つ葉+トマト:高血圧予防
食物繊維の多い食材と組み合わせると、肌荒れ解消に役立ちます。
注意事項
刻んで長時間放置しておくと香りが飛んでしまうので、食べる直前に刻むと効果的です。
民間療法
子供の夜泣きやかんの虫に、三つ葉の葉50gをつぶし、ガーゼに包んでしぼった汁を飲ませます。
名前の由来

1本の茎に3枚ずつ小葉がつくことから、ミツバという名前がつけられました。
別名ミツバセリともいい、セリ科の多年草に属します。もともと山地や原野に自生していたもので、セリに似た香りがあります。
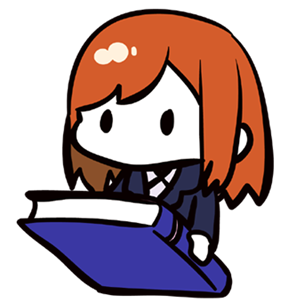





コメント