
注目の成分
カルシウム、カゼイン、ラクトース
期待される効能
骨や歯の強化・潰瘍予防、イライラ解消、骨粗鬆症予防
不眠改善や胃潰瘍の予防にも効果的な牛乳
牛乳は、タンパク質、脂質、鉄分、リン、ビタミンA・B2などを含むバランス食品です。
牛乳は、ストレスや疲労によるダメージを回復して精神を安定させ、不眠やイライラ、疲労感を緩和します。
肺や胃腸に潤いを与えて、のどの渇きや便秘を改善して美肌効果も期待できます。
脂質や炭水化物をエネルギーに変えるビタミンB2も含み、過酸化脂質を抑えて、動脈硬化の予防に効果的です。
乳脂肪には胃の粘膜をコーティングする働きがあり、アルコールなどの刺激から胃粘膜を保護してくれます。
牛乳のカルシウム吸収率
カルシウムは一般的に体に吸収しにくいとされる成分ですが、牛乳においてのカルシウム消化吸収率は40~70%と、群を抜いています。
これは、牛乳中の乳糖やタンパク質の約80%を占めるカゼインホスペプチドが、カルシウムの吸収率を高めてくれるからです。
その為、他の食品よりも効率良くカルシウムを摂取することができます。
牛乳100mg飲んだ時の体内のカルシウム量の増減
牛乳100gには41mgのナトリウムが含まれているので、摂取すると約0.7mgのカルシウムを排外に排出することになります。
その一方で、牛乳100gには110mgのカルシウムが含まれており、牛乳のカルシウム吸収率は40%なので、体内にはおよよ44mgのカルシウムが残ります。
そのため、牛乳100gを飲むと、44mg-0.7mg=43.3mgほど体内のカルシウム量が増加する計算になります。
体内のカルシウムについて
人間の体内のカルシウムの99%は骨中に貯蔵されていますが、血液中のカルシウム濃度が低下すると、骨中のカルシウムが血液中に溶けだしてしまいます。
カルシウムの摂取量が不足した状態が続くと、骨中に貯蔵されているカルシウム量が減り、骨がスカスカになり、骨粗鬆症になる可能性があります。
骨量は20歳をピークに中高年期からしだいに減少していきます。
牛乳の栄養成分
可食部100gあたり 日本食品標準成分表2015年版(七訂)参照
| 普通牛乳 | 加工乳 濃厚 | 加工乳 低脂肪 | |
| エネルギー | 67kcal | 73kcal | 46kcal |
| タンパク質 | 3.3g | 3.5g | 3.8g |
| カリウム | 150mg | 170mg | 190mg |
| カルシウム | 110mg | 110mg | 130mg |
| ビタミンB2 | 0.15mg | 0.17mg | 0.18mg |
| ビタミンC | 1mg | Tr | Tr |
| カフェイン | 0 | 0 | 0 |
| タンニン | 0 | 0 | 0 |
単位:μg(マイクログラム)とは、
1g=1000mg=1000000μg
1μg=0.001mgになります。
Tr:含まれている量が最小記載量に達していない事を示します。
牛乳の種類
牛乳は3種類に大別されています。
「牛乳」は、しぼった生乳を成分無調整で加熱殺菌したもの。
「加工乳」は、生乳を70%以上含み、脂肪分など規定の乳成分を加減したもの。
「乳飲料」は、生乳を20~25%含み、コーヒーや果汁などを加えたもの。
食べ合わせによる相乗効果
牛乳+紅茶:精神安定、イライラ解消
牛乳+小松菜:カルシウム吸収率向上
牛乳+豚肉:骨粗鬆症予防
牛乳に含まれているカルシウムの吸収に役立つのが、豚肉などに含まれている豊富なタンパク質なので、一緒に食べる事で骨粗鬆症予防の効果の向上に期待できます。
注意点
日本人は、成人になるにつれて牛乳の成分を消化するラクターゼという酵素がなくなっていく傾向にあります。
そして、牛乳に含まれる乳糖を完全に消化できる日本人は20%ほどしかいないともいわれています。
日本人は牛乳を消化できる力が弱い人が多いため、乳製品をとっておなかがもたれたり、便がゆるくなったりする場合は飲みすぎに注意が必要になります。
又、牛乳は体を冷やす働きのある食品なので、高血圧や痛風などを患っている人にとっては病気治療に有益ですが、冷え性の方には逆効果となります。



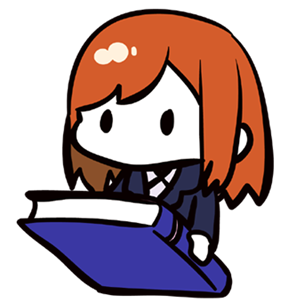


コメント