
注目の成分
βカロテン、アスパラギン酸、リジン
サヤインゲンに期待される効能
抗酸化作用、便秘予防、美容効果、疲労回復、イライラ解消
サヤインゲンのガン予防効果
サヤインゲンには抗酸化作用が高いβカロテンが多く、ビタミンB群、C、カリウムやカルシウムなどが豊富に含まれています。
βカロテンは抗酸化作用が非常に強く、活性酸素を無毒化してガン予防に働く他に、体内で必要なだけビタミンAに変わり、皮膚や粘膜を健康に保つ効果もあります。
栄養バランスのよい緑黄色野菜の予防効果
若いさやには、必須アミノ酸のアスパラギン酸やリジンが含まれており、夏バテ予防、疲労回復や美肌作りの効果に期待できます。
胃の働きを活性化する作用、余分な水分を排出する作用、暑気あたりを改善する作用、腎機能を補い、全身の活力を高める作用があり、むくみや下痢、胃もたれ、食欲不振、に効果的です。
現代栄養学ではビタミンB群やβカロテンなどをバランスよく摂取することを推奨しており、ビタミンB群は総合的にとったほうがよいといわれますが、サヤインゲンの場合、ビタミンB1、B2、B6が含まれているので効率よく摂取できます。
マメ科インゲンマメ属 サヤインゲンの栄養成分
可食部100gあたり 日本食品標準成分表2015年版(七訂)参照
| 若ざや 生 | 若ざや ゆで | |
| 食物繊維 | 2.4g | 2.6g |
| カリウム | 260mg | 270mg |
| カルシウム | 48mg | 57mg |
| βカロテン | 590μg | 580μg |
| ビタミンE | 0.6mg | 0.6mg |
| ビタミンK | 60μg | 51μg |
| ビタミンB2 | 0.11mg | 0.10mg |
| ビタミンC | 8mg | 6mg |
単位:μg(マイクログラム)とは、
1g=1000mg=1000000μg
1μg=0.001mgになります。
日本人の1日に必要な食事での摂取基準量(2015年版)
| 30歳~49歳 男性 | 30歳~49歳 女性 | |||
| 推奨量 | 耐用上限量 | 推奨量 | 耐用上限量 | |
| 食物繊維 | 20g以上 | – | 18g以上 | – |
| カリウム | 3000以上 | – | 2600以上 | – |
| カルシウム | 650mg | 2500mg | 650mg | 2500mg |
| ビタミンA | 900μg | 2700μg | 700μg | 2700μg |
| ビタミンE | 6.5mg | 900mg | 6.0mg | 900mg |
| ビタミンK | 150μg | – | 150μg | – |
| ビタミンB2 | 1.6mg | – | 1.2mg | – |
| ビタミンC | 100mg | – | 100mg | – |
ビタミンAはβカロテン+αカロテン+レチノールの総量になります。
食べ合わせによる相乗効果
サヤインゲン+コンニャク:大腸ガン予防、肥満予防
サヤインゲン+ブロッコリー:ガン予防、美肌づくり、視力回復
サヤインゲン+ほうれん草:便秘予防
サヤインゲン+チンゲン采:血中コレステロール値低下、血圧降下
サヤインゲン+鶏肉:免疫力増強
おいしいサヤインゲンの見分け方
ハリがあり、さやの先までピンとしていて、緑が濃く豆の形がはっきり出ていないものを選びましょう。黒く変色したものや白っぽいものは避けます。
さやがでこぼこしているものは、採り遅れていますが、煮込み料理に使うとおいしく食べられます。
保存方法
なるべく空気に触れないようにキッチンペーパーに包んでからビニール袋に入れて、口をゆるく閉めて冷蔵庫の野菜室で保存します。
すぐに鮮度が落ちるので、使いきれないぶんはその日のうちにサッとゆでて冷凍保存します。
残留農薬除去方法
ザルに入れ、流水の中で1分ほどふり洗いし、表皮の農薬やダイオキシンを落とします。
その後、手でポキンと適当な長さに折り(切り)、沸騰したお湯で1分ほどゆで、ゆでこぼします。
日本で使用されている農薬は、一定の安全基準を満たしていますが、害が全く無いというわけではなく、中には発ガン性が指摘されているものもあるようです。又、ダイオキシンは、塩素・水素・炭素・酸素からなり、これらの元素が入ったゴミを燃やす事で発生し、大気を汚染したダイオキシンには、発ガン性の危険があり食物に付着して、それを食べる事で人体に影響が出ると言われています。
調理のコツ
ゆでる場合は、さや全体に塩を振って板ずりし、たっぷりのお湯に塩を入れてゆでると、ゆで上がりも色鮮やかになります。
原産地
サヤインゲンの原産地は、中央アメリカからメキシコになり、紀元前から栽培されています。
豆よりも若いさやを好んだイタリア人によって欧州に広がり、日本へは江戸時代に中国の高僧、隠元禅師によって伝えられました。
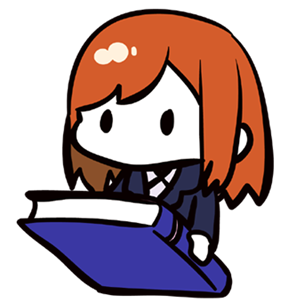





コメント