
注目の成分
カリウム
トウガンに期待される効能
血圧調整作用、利尿作用、肝機能強化、むくみ解消、夏バテ防止
体にたまった熱を冷ます効果が高く、糖尿病にも効果的
抗酸化作用があるビタミンCも含む為、風邪の予防に期待でき、体の余分な熱を取り除く働きがあるので、夏バテ解消に有効です。
カリウムを豊富に含んでいるので、体内の余分なナトリウムを排出して血圧を正常に保ち、体内の水分代謝を高める作用があるので、高血圧予防に期待できます。
腎臓での老廃物の排泄をうながす作用もあるので、むくみの解消に役立ちます。
トウガンの95%以上は水分なので尿量を増やし利尿に役立ち、低カロリー食材で新陳代謝を促す成分が含まれているので、ダイエットなどには効果的な食材となっています。
皮を乾燥したものは「冬瓜皮(とうがひ)」、種を乾燥したものは「冬瓜仁(とうがにん)」又は「冬瓜子(とうがし)」と呼ばれ、いずれもむくみや咳、痰、腫れ物、下痢などに用いられる漢方薬になっているほど薬効に期待されています。
ウリ科 冬瓜(トウガン)の栄養成分
可食部100gあたり 日本食品標準成分表2015年版(七訂)参照
| 冬瓜 果実 生 | 冬瓜 果実 ゆで | |
| 食物繊維 | 1.3g | 1.5g |
| カリウム | 200mg | 200mg |
| カルシウム | 19mg | 22mg |
| βカロテン | 0 | 0 |
| ビタミンE | 0.1mg | 0.1mg |
| ビタミンK | 1μg | Tr |
| ビタミンB2 | 0.01mg | 0.01mg |
| ビタミンC | 39mg | 27mg |
単位:μg(マイクログラム)とは、
1g=1000mg=1000000μg
1μg=0.001mgになります。
Tr:含まれている量が最小記載量に達していない事を示します。
日本人の1日に必要な食事での摂取基準量(2015年版)
| 30歳~49歳 男性 | 30歳~49歳 女性 | |||
| 推奨量 | 耐用上限量 | 推奨量 | 耐用上限量 | |
| 食物繊維 | 20g以上 | – | 18g以上 | – |
| カリウム | 3000以上 | – | 2600以上 | – |
| カルシウム | 650mg | 2500mg | 650mg | 2500mg |
| ビタミンA | 900μg | 2700μg | 700μg | 2700μg |
| ビタミンE | 6.5mg | 900mg | 6.0mg | 900mg |
| ビタミンK | 150μg | – | 150μg | – |
| ビタミンB2 | 1.6mg | – | 1.2mg | – |
| ビタミンC | 100mg | – | 100mg | – |
ビタミンAはβカロテン+αカロテン+レチノールの総量になります。
食べ合わせによる相乗効果
トウガン+油揚げ:老化防止、スタミナアップ
トウガン+豆腐:利尿効果、腎臓病予防、夏バテ解消
トウガン+タマネギ:動脈硬化予防
トウガン+トウモロコシ:むくみ解消
トウガンには体温を下げる働きがあるので、タンパク質やビタミンB1が多く活力源となる鶏肉や豚肉と炊き合わせると、夏バテ防止に効果的です。
トウガンの選別の仕方
もってみて、ずっしりとした重みのあるもので、緑が濃く、星型文様がはっきりしたものを選びましょう。
割ってあるものは、タネのしっかり詰まっているものを選びましょう。
皮の表面全体に粉をふいているものが完熟しています。
保存方法
皮をむき、中心の種とワタの部分を取り除き、使いやすいサイズにカットしてラップをして冷蔵保存、又は冷凍保存します。
丸のままなら冷暗所で長期保存が可能です。
民間療法
夏バテや発熱、のどの渇き、食あたりなどには、生のしぼり汁を飲むと効果があるといわれています。
又、生のしぼり汁に、ハチミツを少量加えたものを飲めば利尿作用によって、尿の出がよくなるとされています。
注意事項
生のにんじんやきゅうりにはビタミンC分解酵素が含まれているので、トウガンと組み合わせた料理はひかえましょう。
トウガンは体を冷やす作用が強いので、冷え性の人や、胃腸の弱い人、妊婦などは食べすぎに注意しましょう。
名前の由来
漢字では冬瓜なので、冬に野菜のように感じますが、旬は7月~9月で夏の野菜になります。皮が厚く、丸のまま冷暗所に保存しておけば、冬まで保存しておけることや、霜が降りた後に、粉を吹いたように白くなることから、冬瓜(トウガン)とういう名前がついたといわれています。
原産地は東南アジア、インド地方、南洋諸島など諸説ありますが、日本では平安時代の「本草和名」に記載があることから、800年も前から日本に親しまれた野菜だといわれています。
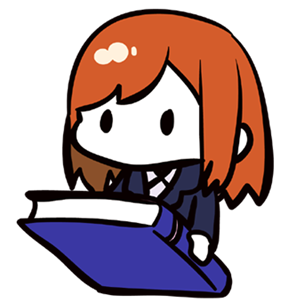





コメント