
ナスに含まれる注目の成分
デルフィニジン、ナスニン
ナスに期待される作用
視力改善、コレステロール値低下、生活習慣病予防、むくみ改善
皮の部分に含まれるナスニンに強力な抗酸化作用のナス
ナスには、アントシアニンの一種でデルフィニジンという栄養素が含まれています。
デルフィニジンは抗酸化作用が非常に強く、視力改善に効く過酸化脂質の産生を抑制するといわれています。
又、視力を回復を助ける働きの他、動物実験では、発ガン促進物質を抑制する作用がある事が確認されています。
紫色はポリフェノールの一種であるナスニンという栄養素で、抗酸化作用があり細胞のガン化を抑制したり、コレステロール値を下げる働きがあります。
ガン予防に効果的なクロロゲン酸も豊富に含まれており、ナスニンと同様に皮の部分に多く含まれています。
ナスに含まれるプロテアーゼインヒビターの物質には、発ガン物質が体内で働かないようにする作用があるほか、炎症をしずめる効果があります。
動脈硬化・高血圧・血栓症の予防に効果的なナス
ナスには、ミネラルバランスを整えるカリウム、骨や歯をつくるカルシウムやマグネシウム、鉄欠乏性貧血を予防する鉄、免疫力を高める亜鉛、銅、マンガンなどがバランスよく含まれています。
油をよく吸収する性質がありますが、油で調理すると水溶性の色素成分のナスニンの流出が抑えられ、おいしさや栄養素を閉じ込める事ができます。そして、夏バテや食欲減退気味の時には、炒めものなどにすると効果的です。
ナスに含まれている色素には、コレステロールの上昇を抑える働きがあり、動脈硬化や糖尿病など生活習慣病の予防効果が期待されています。
ナスに含まれるプロテアーゼインヒビターの炎症をしずめる効果は、口から腸まで消化器系全般に及びます。
口内の温度を下げるとともに、粘膜にできた潰瘍を治す働きがある為、口内炎に対して効果が期待されています。
又、神経の興奮を抑えたり、神経痛や関節痛の痛みをしずめるのに、すぐれた効果を発揮します。
90%以上が水分でビタミンやミネラル類はあまり多く含まれていませんが、体の熱を取る作用があり、古くから暑気払いによいとされてきました。
ナス科ナス属 ナスの栄養成分
可食部100gあたり 日本食品標準成分表2015年版(七訂)参照
| ナス:ゆで | ナス:油炒め | 1日の食事で必要な推奨量 | ||
| 男性 30歳~49歳 | 女性 30歳~49歳 | |||
| 食物繊維 | 2.1g | 2.6g | 20g以上 | 18g以上 |
| カリウム | 180mg | 290mg | 3000mg以上 | 2600mg以上 |
| カルシウム | 20mg | 22mg | 650mg | 650mg |
| βカロテン | 98μg | 190μg | 900μg | 700μg |
| レチノール | 8μg | 16μg | ||
| ビタミンD | 0 | 0 | 5.5μg | 5.5μg |
| ビタミンE | 0.3mg | 3.3mg | 6.5mg | 6.0mg |
| ビタミンK | 10μg | 11μg | 150μg | 150μg |
| ビタミンB2 | 0.04mg | 0.07mg | 1.6mg | 1.2mg |
| ビタミンB12 | 0 | 0 | 2.4μg | 2.4μg |
| 葉酸 | 22μg | 36μg | 240μg | 240μg |
| ビタミンC | 1mg | 2mg | 100mg | 100mg |
単位:μg(マイクログラム)とは、
1g=1000mg=1000000μg
1μg=0.001mgになります。
ナスの原産地はインドで、日本へは中国から渡来し、奈良時代から全国で広く栽培が始まりました。
食べ合わせによる相乗
ナス+とうがらし:夏バテ解消
ナス+きのこ:肥満予防
ナスの保存方法
低温に弱いので、新聞紙に包んで常温で保存します。
冷蔵庫に入れる場合は、ポリ袋に入れて野菜室で保存します。
ナスを調理する前の不純物除去方法
ナスは病害虫に強く、比較的早く育つため、農薬は余り使用されていないようですが、おいしさが増すのでアク抜きはしたほうがよいとされます。
流水で30秒ほどこすり洗いして、切ったらすぐに水に浸けて、水が黒ずんでくるまでアク抜きをします。薄切りにするほど農薬などの不安物質除去の効果が高くなります。
注意事項
体を冷やす作用が強いので、冷え性や胃腸が弱い人は食べすぎると冷えすぎてお腹をこわす事があるので注意が必要です。
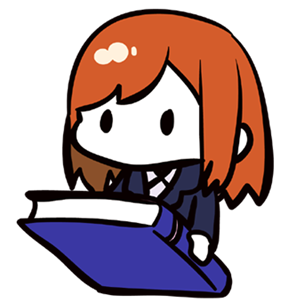




コメント