
注目の成分
セサミン、セサモリン、アントシアニン、セレン
ゴマに期待される効能
肝臓ガン予防、大腸ガン予防、抗酸化作用、健脳効果、動脈硬化予防、美肌保持、便秘予防
ゴマの抗酸化作用
ゴマに含まれるセサミンは強力な抗酸化作用があり、肝機能を強化し肝臓ガンの発生をおさえる効果があります。
セサモリンは炒めることでセサモールという、より抗酸化作用の高い成分を生成します。
ゴマに含まれるセサミノール配糖体には抗酸化作用がありませんが、消化・吸収されると、腸内細菌の働きでセサミノールに変換され、抗酸化作用が発生します。
抗酸化ビタミンのビタミンEも豊富に含まれており、強い抗酸化作用でガンを予防するセレンも含まれています。
ゴマの脂質の40%は大腸ガンの予防効果があるオイレン酸が占めています。
老化を防ぐ伝統的な健康食品のゴマ
ゴマにはリノール酸やリノレン酸などの人体で合成できない必須脂肪酸が含まれており、リノール酸やオレイン酸などの不飽和脂肪酸が血中コレステロールの上昇を抑える働きがあります。
セサミノール配糖体にもコレステロールの沈着を抑え、動脈硬化を予防することが動物実験で確認されています。
抗酸化作用の高いゴマリグナンに含まれるセサミンには、老化防止、肝機能の改善、血圧降下などの効果に期待できます。
健脳効果のあるアミノ酸や骨粗鬆症を予防するカルシウムも豊富に含まれています。
ゴマにはカルシウム、ビタミン類が多く含まれており、神経の高ぶりをしずめる働きがあり、月経に伴う精神的なイライラの解消に期待できます。
ゴマ科ゴマ属 ゴマの栄養成分
可食部100gあたり 日本食品標準成分表2015年版(七訂)参照
| ごま いり | ごま むき | |
| 食物繊維 | 12.6g | 13.0g |
| カリウム | 410mg | 400mg |
| カルシウム | 1200mg | 62mg |
| βカロテン | 17μg | 2μg |
| ビタミンE | 24.1mg | 32.5mg |
| ビタミンK | 12μg | 1μg |
| ビタミンB2 | 0.23mg | 0.14mg |
| ビタミンC | Tr | 0 |
単位:μg(マイクログラム)とは、
1g=1000mg=1000000μg
1μg=0.001mgになります。
Tr:含まれている量が最小記載量に達していない事を示します。
日本人の1日に必要な食事での摂取基準量(2015年版)
| 30歳~49歳 男性 | 30歳~49歳 女性 | |||
| 推奨量 | 耐用上限量 | 推奨量 | 耐用上限量 | |
| 食物繊維 | 20g以上 | – | 18g以上 | – |
| カリウム | 3000以上 | – | 2600以上 | – |
| カルシウム | 650mg | 2500mg | 650mg | 2500mg |
| ビタミンA | 900μg | 2700μg | 700μg | 2700μg |
| ビタミンE | 6.5mg | 900mg | 6.0mg | 900mg |
| ビタミンK | 150μg | – | 150μg | – |
| ビタミンB2 | 1.6mg | – | 1.2mg | – |
| ビタミンC | 100mg | – | 100mg | – |
ビタミンAはβカロテン+αカロテン+レチノールの総量になります。
白ゴマ

地域を問わず世界中で幅広い用途で利用されており、油分が多い為ゴマ油を作るのに適しています。
ゴマ和えやゴマ豆腐に使われる、もっとも一般的なゴマで、風味はマイルドですが、品質にはバラツキがあるようです。
白ゴマは体を潤す働きが高くなり、肌の乾燥を解消したり、便秘の改善に効果的です。
黒ゴマ

ゴマはもともと黒ゴマが原種です。
赤飯やおはぎ、ゴマ和えに使われ、香りが高く、白ゴマにはないアントシアニンを皮に含んでいます。
黒ゴマには、肝や腎の機能を向上させて血や生命力を補う作用があり、滋養強壮やアンチエイジングに効果があり、長生不老食と呼ばれています。
金ゴマ

ゴマの中で一番香りが高く、懐石料理などで使用されてきました。
種皮はフラボノイドを含み、抗菌作用があります。
食べ合わせによる相乗効果
ゴマ+かぼちゃ:ガン予防、老化防止
ゴマ+大豆:骨粗鬆症予防、健脳効果
ゴマ+わかめ:便秘予防、血行促進
ゴマ+マグロ:認知症予防、健脳効果
黒ゴマ+ハチミツ:老化防止
白ゴマ+ほうれんそう:便秘解消
白ゴマ+酢:骨粗しょう症予防
栄養分をしっかり摂るには、すってかたい皮を壊して食べる事が重要ですが、空気に触れるとせっかくのリノール酸やオレイン酸が酸化するので、使う直前に用意するほうが良質な脂肪酸を摂取できます。
ゴマの保存方法
ゴマは湿気が大敵なので、開封後は密閉容器などに入れて冷暗所や夏場は冷蔵庫で保存します。
ゴマの歴史
原産地はアフリカのサバンナ地帯です。
日本には、中国から伝わり、奈良時代にはすでに重要な農作物となっていました。
中国に、ゴマとハチミツを混ぜて作った「静神丸(せいしんがん)」という不老長寿の秘薬があり、「百日間服用すると一切の病気を除く」といわれ、達磨大師が9年間座禅を組んでいたとき唯一口にしたもので、体にとって必要な養分を過不足なく含む完全食といわれています。
中国の薬物書「本草綱目(ほんぞうこうもく)」にも「気力を増し、皮膚をなめらかにし、筋骨を強化し、眼や耳の働きをよくし、肺を潤し、胃腸の機能を高め、大小便の出を促し、長く食せば老化を防ぐ」と記され、ほぼ万能の効能があるとされます。
ごま化す
ごまあえ、ゴマ塩、ゴマみそなど応用範囲は広く、ゴマを加えて味が損なわれるものは無いといわれています。
「ごまかす」というのは、どんな食品も、ゴマを用いれば美味しく変化して、ごまかす事ができるという意味からきている説があります。
又、江戸時代にお店でうどん粉にゴマをまぶした焼き菓子が売り出されており、ゴマの香ばしいにおいがして美味しそうだったので食べてみると、中身が空っぽで美味しくはなかったようです。
その事より、ずるや真実を隠す事を「ごま菓子の類だ」というようになり、それが転じて「ごまかす」と言われるようなったという説もあります。
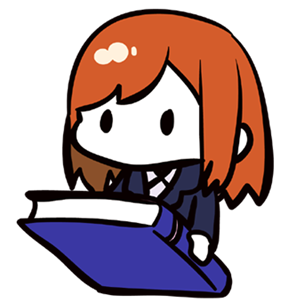





コメント