
注目の成分
鉄、グリコーゲン、タウリン、オクタデセン酸
蜆(シジミ)に期待される効能
肝機能強化、貧血改善、乳汁分泌の促進、コレステロール低下、眼精疲労予防
二日酔いを解消する肝臓の薬として有名なシジミ

シジミには、カルシウム、鉄、ビタミンB2、ビタミンB12など日本人に不足しがちな栄養成分が豊富に含まれています。
タウリン、グリコーゲン、メチオニン、コハク酸、ビタミンB12、オクタデセン酸により肝機能を強化し黄疸を改善して、飲酒時の悪酔いや二日酔い防止に役立ちます。
又、オチアミンやタウリンなどの成分はコレステロールと結びついて、胆汁の分泌を促し、肝臓の解毒作用を活発にして肝臓の働きそのものを強化します。
シジミに含まれる鉄は貧血に効き目を発揮し、ビタミンB12は造血作用にすぐれているので、貧血予防に効果的です。
高血圧、低血圧などの血圧異常を調整する作用や体内にたまったニコチンなどを排出する作用に期待できます。
シジミ科 シジミの栄養成分

可食部100gあたり 日本食品標準成分表2015年版(七訂)参照
| しじみ 生 | しじみ 水煮 | |
| 食物繊維 | 0 | 0 |
| カリウム | 83mg | 66mg |
| カルシウム | 240mg | 250mg |
| βカロテン | 97μg | 220μg |
| レチノール | 33μg | 76μg |
| ビタミンD | 0.2μg | 0.6μg |
| ビタミンE | 1.7mg | 3.9mg |
| ビタミンK | 2μg | 5μg |
| ビタミンB2 | 0.44mg | 0.57mg |
| ビタミンC | 2mg | 1mg |
| DHA | 53mg | 140mg |
| EPA(IPA) | 41mg | 110mg |
単位:μg(マイクログラム)とは、
1g=1000mg=1000000μg
1μg=0.001mgになります。
日本人の1日に必要な食事での摂取基準量(2015年版)
| 30歳~49歳 男性 | 30歳~49歳 女性 | |||
| 推奨量 | 耐用上限量 | 推奨量 | 耐用上限量 | |
| 食物繊維 | 20g以上 | – | 18g以上 | – |
| カリウム | 3000mg以上 | – | 2600mg以上 | – |
| カルシウム | 650mg | 2500mg | 650mg | 2500mg |
| ビタミンA | 900μg | 2700μg | 700μg | 2700μg |
| ビタミンD | 5.5μg | 100μg | 5.5μg | 100μg |
| ビタミンE | 6.5mg | 900mg | 6.0mg | 900mg |
| ビタミンK | 150μg | – | 150μg | – |
| ビタミンB2 | 1.6mg | – | 1.2mg | – |
| ビタミンC | 100mg | – | 100mg | – |
食べ合わせによる相乗効果

シジミ+水菜:咳止め
シジミ+ショウガ:肝機能向上
シジミ+豆腐:貧血改善
シジミ汁の効果

みそに含まれる各種アミノ酸はシジミのアミノ酸と組み合わさると、さらに理想的なアミノ酸構成になり、タウリンやグリコーゲンが肝機能を整えるので二日酔いなどに効果的です。
また味噌の消化酵素がシジミの消化を助けてくれる効果もあります。汁にうま味や栄養素が溶け出しているので汁まで摂取しましょう。
砂抜きの方法
ボウルに約1%の食塩水(水1リットルに塩小さじ2程度)に浸します。
アサリと違い汽水域に生息しているので真水でも可能ですが、うま味が逃げてしまうので1%の食塩水に浸します。
アサリやハマグリの砂抜きの塩分濃度は3%程度となっています。

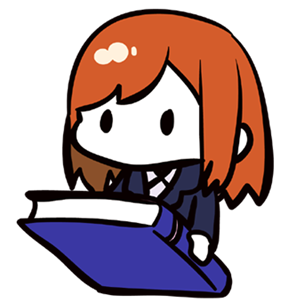





コメント