
注目の成分
食物繊維、βカロテン、ペクチン
オクラに期待される作用
動脈硬化予防、がん予防、疲労回復、整腸作用
ペクチンが注目成分のオクラ
オクラに含まれる水溶性食物繊維の一種のペクチンは、腸内の有害物質を排出させる働きがあり便秘を改善したり、ガン予防に役立ちます。
又、糖分の消化吸収の速度を緩やかにして血糖値を安定させる働きもあります。
糖タンパク質のネバネバ成分には、タンパク質の吸収を助ける働きがあり、疲労回復や滋養強壮に有効です。
オクラは粘膜の強化・整腸作用・動脈硬化予防・血中コレステロール値低下の効果に期待できます。
アオイ科トロロアオイ属 オクラの栄養成分
可食部100gあたり 日本食品標準成分表2015年版(七訂)参照
| オクラ 生 | オクラ ゆで | 1日の食事で必要な推奨量 | |
| 男性 30歳~49歳 | |||
| 食物繊維 | 5.0g | 5.2g | 20g以上 |
| カリウム | 260mg | 280mg | 3000mg以上 |
| カルシウム | 92mg | 90mg | 650mg |
| βカロテン | 670μg | 720μg | 900μg |
| レチノール | 56μg | 60μg | |
| ビタミンD | 0 | 0 | 5.5μg |
| ビタミンE | 1.2mg | 1.2mg | 6.5mg |
| ビタミンK | 71μg | 75μg | 150μg |
| ビタミンB2 | 0.09mg | 0.09mg | 1.6mg |
| ビタミンB12 | 0 | 0 | 2.4μg |
| 葉酸 | 110μg | 110μg | 240μg |
| ビタミンC | 11mg | 7mg | 100mg |
単位:μg(マイクログラム)とは、
1g=1000mg=1000000μg
1μg=0.001mgになります。
食べ合わせによる相乗効果
オクラ+牛肉:夏バテ予防
オクラ+鶏肉+じゃがいも:食欲増進
オクラ+納豆:免疫力向上、便秘解消
保存方法
乾燥と低温に弱いので、ポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存します。
注意事項
食物繊維が豊富なので、胃腸の調子が悪いときや下痢をしている時に食べると症状が悪化する可能性があるので注意しましょう。
水溶性食物繊維について
食物繊維には水に溶けやすい水溶性食物繊維と、水に溶けない不溶性食物繊維があり、糖質の一種で栄養素としては炭水化物に分類されます。
水溶性食物繊維はブドウ糖の吸収を緩やかにして、コレステロールの吸収を抑制し、余分なコレステロールの排泄を促すといった働きがあります。
不溶性食物繊維のほとんどは植物の細胞壁なので、水分を吸収することで、腸の運動を活発にして便秘改善などに効果があります。
腸内環境を整えるためには、食物繊維が必要ですが、不溶性食物繊維の野菜を大量に摂りすぎると腸に負担をかけてしまいます。
水溶性食物繊維を多く含む食品(100g中の分量:単位g)
| にんにく | 3.7g |
| ごぼう | 2.7g |
| 納豆 | 2.3g |
| レモン | 2.0g |
| アボカド | 1.7g |
| オクラ | 1.6g |
| あしたば | 1.5g |
| 芽キャベツ | 1.4g |
不溶性食物繊維を多く含む食品(100g中の分量:単位g)
| いんげん豆 | 11.8g |
| ひよこ豆 | 11.1g |
| おから | 11.1g |
| あずき | 11.0g |
| くり | 7.5g |
| えんどう豆 | 7.2g |
| よもぎ | 6.9g |
| こしあん | 6.5g |
多種多様な栄養素を摂取して効率よく利用する事で、人間の体は整っています。
炭水化物がエネルギーに変わるにはビタミンB群などが必要になり、ビタミンB群が活性化するにはアミノ酸やミネラルが必要になります。
それぞれの素材に含まれている栄養成分を効率よく体に取り込む為には、多種類の食品でバランスよく栄養素を摂取する事でプラスアルファの効果が期待できるようです。
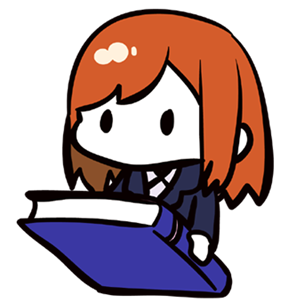





コメント