
注目の成分
リンゴ酸、βカロテン、クロロゲン酸
ビワに期待される効能
ガン予防、生活習慣病予防、疲労回復、肌荒れ解消、視力低下予防
葉も果肉も万病を治すとされるビワ

βカロテンとクリプトキサンチンの含有量は果物の中でもトップクラスで、高血圧、脳梗塞、心筋梗塞、生活習慣病予防やガン予防、皮膚や粘膜の健康に役立ちます。
ポリフェノールの一種のクロロゲン酸には、ガン予防効果に期待できます。
ビワの葉に含まれるアミグダリンは、血液を浄化して、炎症やガン細胞を除去することが期待されています。
種にはアミグダリンが葉の1300倍も含まれており、ビワ酒にして患部に塗ったり、飲んだりして役立てています。
リンゴ酸、クエン酸、ビタミンCを含み、疲労回復や風邪予防、美肌づくりに期待されます。
熱を取り、のどの渇きを癒す作用があり、気がのぼって起こる吐き気や胸やけ、イライラ、のぼせを解消して、胃もたれや食欲不振の改善に役立ちます。
バラ科ビワ属 ビワの栄養成分

可食部100gあたり 日本食品標準成分表2015年版(七訂)参照
| ビワ 生 | ビワ 缶詰 | 1日の食事で必要な推奨量 | ||
| 男性30~49歳 | 女性30~49歳 | |||
| 食物繊維 | 1.6g | 0.6g | 20g以上 | 18g以上 |
| カリウム | 160mg | 60mg | 3000mg以上 | 2600mg以上 |
| カルシウム | 13mg | 22mg | 650mg | 650mg |
| βカロテン | 810μg | 470μg | 900μg | 700μg |
| レチノール | 68μg | 39μg | ||
| ビタミンD | 0 | 0 | 5.5μg | 5.5μg |
| ビタミンE | 0.1mg | 0.2mg | 6.5mg | 6.0mg |
| ビタミンK | 0 | 0 | 150μg | 150μg |
| ビタミンB2 | 0.03mg | 0.01mg | 1.6mg | 1.2mg |
| ビタミンB12 | 0 | 0 | 2.4μg | 2.4μg |
| 葉酸 | 9μg | 9μg | 240μg | 240μg |
| ビタミンC | 5mg | Tr | 100mg | 100mg |
単位:μg(マイクログラム)とは、
1g=1000mg=1000000μg
1μg=0.001mgになります。
Tr:含まれている量が最小記載量に達していない事を示します。
おいしいビワの見分け方
鮮やかなだいだい色で、表面にツヤがあり、うぶ毛とブルームといわれる白い粉が残っているものが新鮮で、弾力があり、左右対称にふくらんでいるものが良品です。
保存方法

常温で保存します。冷やしたい場合は食べる直前に冷蔵庫に入れます。
低温にも高温にも弱く傷みやすいので、3日以内に食べきりたい果物です。
食べ合わせによる相乗効果

ビワ+キウイフルーツ:風邪予防
ビワ+ライチ:イライラ解消、のぼせ解消
ビワ+あんず:咳止め
ビワ+ごま:疲労回復
ビワ+焼酎:免疫力向上
民間療法

咳が出るときは、実に砂糖を加えて煮詰めたものを飲むと咳がやわらぐといいます。
葉を陰干しして細かくしたものを煎じて飲んで、疲労回復や食欲増進に役立てました。
ビワの葉茶
ティーバックでも市販されており、クセもなく飲みやすく、ポリフェノール作用で美肌効果に期待できます。
「大薬王樹(だいやくおうじゅ)」と呼ばれていたビワ

三千年前のインドの古い仏典に、ビワは生けとし生けるものの万病を治す植物として登場します。
果肉は肺を潤して口の渇きや咳を除き、胃腸の働きを整えて嘔吐を止めるとされます。
葉には咳や痰を除き、尿の出を促し、暑気を払い、食中毒や下痢に効果があるとされます。
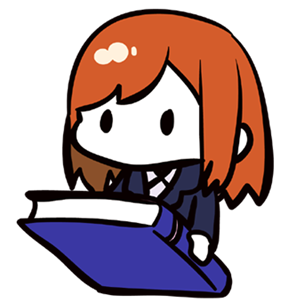





コメント