
注目の成分
レシチン、カリウム
そら豆に期待される効能
血栓予防、疲労回復、貧血防止、血圧降下予防、便秘解消
栄養価が高く貧血予防に働く鉄やミネラルを含むそら豆
そら豆には体の組織を作るタンパク質やビタミンB1、B2、Cなどのほか、カリウム、鉄、銅などのミネラル類が多く含まれ、美肌効果、疲労回復や貧血予防に効果が期待されます。
皮には豆よりも多くの食物繊維が含まれており、皮ごと食べれば便秘の解消に役立ちます。
レシチンには血栓を溶かす効果があり、ビタミンB2とともに働いて血中コレステロールの酸化を防ぎます。
胃の中の余分な水分を代謝し、食欲不振や胃もたれを解消して、栄養価も高いので疲労回復に効果的です。
そら豆は腎の働きを活性化し、水分代謝を高めて尿の出をよくして、むくみをとり去る効果があり、腎の低下は老化の一因となるので、そら豆は老化防止に役立つといわれています。
マメ科ソラマメ属 そら豆の栄養成分
可食部100gあたり 日本食品標準成分表2015年版(七訂)参照
| 全豆 乾 | しょう油豆 | 未熟豆 ゆで | |
| 食物繊維 | 9.3g | 10.1g | 4.0g |
| カリウム | 1100mg | 280mg | 390mg |
| カルシウム | 100mg | 39mg | 22mg |
| βカロテン | 5μg | 4μg | 210μg |
| ビタミンE | 0.8mg | 2.0mg | 1.2mg |
| ビタミンK | 13μg | 9μg | 19μg |
| ビタミンB2 | 0.20mg | 0.09mg | 0.18mg |
| ビタミンC | Tr | 0 | 18mg |
単位:μg(マイクログラム)とは、
1g=1000mg=1000000μg
1μg=0.001mgになります。
Tr:含まれている量が最小記載量に達していない事を示します。
日本人の1日に必要な食事での摂取基準量(2015年版)
| 30歳~49歳 男性 | 30歳~49歳 女性 | |||
| 推奨量 | 耐用上限量 | 推奨量 | 耐用上限量 | |
| 食物繊維 | 20g以上 | – | 18g以上 | – |
| カリウム | 3000以上 | – | 2600以上 | – |
| カルシウム | 650mg | 2500mg | 650mg | 2500mg |
| ビタミンA | 900μg | 2700μg | 700μg | 2700μg |
| ビタミンE | 6.5mg | 900mg | 6.0mg | 900mg |
| ビタミンK | 150μg | – | 150μg | – |
| ビタミンB2 | 1.6mg | – | 1.2mg | – |
| ビタミンC | 100mg | – | 100mg | – |
ビタミンAはβカロテン+αカロテン+レチノールの総量になります。耐用上限量は野菜などの食材で摂取する場合は問題ないですが、サプリメントなどで摂取した場合に悪影響が発生する可能性のある数値になります。
食べ合わせによる相乗効果
そら豆+唐辛子:腎臓病予防、便秘予防
そら豆+きくらげ:動脈硬化予防、強肝作用、心臓病予防
そら豆+きゅうり:利尿作用、腎臓病予防、むくみ解消
そら豆+牡蠣:貧血防止、体力回復、スタミナ増強
そら豆+ごはん:夏バテ予防、疲労回復
そら豆+とうもろこし:むくみ解消
新鮮なそら豆び選び方
さやの緑色が濃く、張りとツヤがあり、さやの上から見て豆の形がはっきりわかり、大きさがそろっているものが良品です。
中のワタが詰まっているほど新鮮です。
さやの背すじが茶色いものは避けましょう。
保存方法
鮮度が落ちるのが早く乾燥に弱いのでポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存します。
収穫した瞬間から栄養価が落ちるので、新鮮なものを購入してすぐに調理又はかためにゆでて冷凍保存したい食材です。
ゆで方
たっぷりのお湯を沸かして塩と酒少々を入れてゆでます。酒によってそら豆の青臭さがやわらぎます。
2分程度ゆでて、ざるにとって自然に冷まします。余熱があるので少しかためにゆでても大丈夫です。
しょう油豆
香ばしく炒ったそら豆を甘辛く煮たもので、讃岐地方の郷土料理です。
唐辛子が効いており、煮豆とは食感が異なり、やや集めの皮をかむと口の中でボロボロと崩れるのが特徴です。
そら豆の原産地
北アフリカからカスピ海沿岸が原産地で、世界最古の農作物のひとつです。
日本に渡来したのは奈良時代で、インドの僧が渡来した時に持参し、それを遊行僧が各地に広めたといわれています。
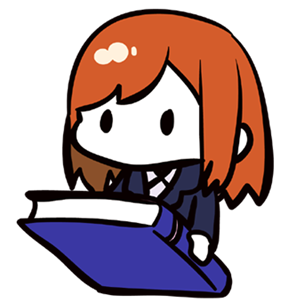





コメント